2025年8月、北海道で初めて重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の感染者が確認されました。これまで西日本を中心に報告されてきたSFTSが、ついに北の大地にまで広がったことになります。
このニュースは、単に「北海道にも感染が来た」という事実以上に、私たち全員が日常生活やレジャー、そしてペットとの接し方を見直す必要があることを意味しています。
SFTSとは?
SFTS(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)は、ウイルスを保有するマダニによって媒介される感染症です。
主な症状は以下の通りです。
- 発熱
- 頭痛
- 嘔吐・下痢などの消化器症状
- 出血症状(皮下出血、下血)
- 神経症状(意識障害、失語など)
致死率は6.3~30%と高く、現時点では有効なワクチンや特効薬は存在しません。治療は対症療法に限られ、重症化すれば命に関わる恐れがあります。
北海道での初確認が意味すること
今回の患者は60代男性で、道央地域に居住。7月中旬以降、道外への移動はなく、日常的に草木に触れる機会があったとのこと。本人も「ダニにかまれた」と証言しています。
北海道でもマダニは以前から存在していましたが、問題はウイルスを持つマダニが道内に定着し始めた可能性があることです。
マダニは鳥や動物にくっついて長距離移動するため、地域の境界はあってないようなもの。九州・四国・中国地方から、関東、そして北海道へと、感染リスクの地理的制限は急速に薄れています。
感染経路は「野外」だけではない
SFTSというと「山や畑でダニにかまれる」というイメージが強いですが、それだけではありません。実は、感染したイヌやネコを介して人間に感染するケースもあります。
ペットを介した感染のリスク
- 感染した動物の血液、唾液、排泄物に接触
- ペットに寄生したマダニに直接かまれる
特に猫は、外に出て狩りをする習性があるため、マダニを連れて帰ることがあります。犬も同様に、散歩中に草むらへ入り込むことでダニに寄生される可能性があります。
マダニの特徴と活動時期
マダニの成虫は吸血前で3〜8mm程度ですが、吸血後は10〜20mmまで肥大します。長い場合は10日以上も血を吸い続けます。
活動時期は春から秋。特に気温が高く湿度のある環境を好みます。草むらややぶ、落ち葉の下などに潜み、通りかかった動物や人間に飛びつきます。
感染予防の基本対策
1. 野外活動時の服装
- 長袖・長ズボンで肌の露出を減らす
- 裾は靴下やブーツの中に入れる
- 帽子・手袋の着用も有効
2. 虫よけの使用
ディートやイカリジンを含む虫よけスプレーは、マダニ対策にも有効です。ただし、完全に防げるわけではないため、服装対策と組み合わせることが重要です。
3. 活動後のチェック
- 家に入る前に衣服をはたく
- 入浴時に全身を鏡でチェック
- ペットの場合も毛をかき分けて皮膚を確認
ペットと暮らす人の注意点
屋外に出る犬・猫のマダニ対策
- 動物病院で処方されるマダニ駆除薬の定期使用
- 散歩や外出後のブラッシング
- 草むらややぶへの進入を避ける
感染したペットへの接触注意
SFTSに感染した動物は、発熱や元気消失、出血症状を示すことがあります。疑わしい場合は直ちに動物病院へ。
むやみに触れたり、看病時に素手で接触するのは危険です。
畑仕事・アウトドアでの特別な注意
畑作業の場合
- 作業服は作業後すぐに洗濯
- 草刈り作業では特にマダニが多く潜むため、首や手首の防御も忘れずに
アウトドアレジャー(キャンプ・登山)
- テント設営地は草が短い場所や整地された場所を選ぶ
- レジャー後は帰宅前に衣服や荷物を確認し、ダニの持ち帰りを防ぐ
媒介動物と地域拡大の背景
マダニは自力で広範囲を移動することはできませんが、野鳥やシカ、イノシシなどの野生動物に付着して移動します。
温暖化により北海道の気温が上昇し、マダニの活動期間や生息範囲が拡大していると考えられます。
感染拡大を防ぐために
- 「自分は山に行かないから大丈夫」という油断は禁物
- 庭や畑、近所の公園でも感染リスクはある
- ペットを外に出す家庭は、特に注意が必要
まとめ
SFTSは、これまで西日本を中心に報告されてきましたが、すでに全国的な感染症へと変わりつつあります。
畑仕事やアウトドアレジャーだけでなく、ペットとの日常的なふれあいの中にも感染の危険は潜んでいます。
特効薬やワクチンがない今、私たちにできるのは予防だけです。
服装・虫よけ・活動後のチェック・ペット対策を習慣にすることで、SFTSの脅威を最小限に抑えることができます。
特許アイデア名
「畑・アウトドア・ペット対応型マダニ感染予防システム」
発明の背景
マダニは春〜秋にかけて活動が活発化し、SFTSをはじめとする感染症を媒介する。これまで、野外作業者やハイカー向けの予防具はあったが、ペットを介した家庭内感染リスクに着目した包括的対策は不足していた。特に、畑作業やアウトドア後に、衣服やペットを通じてマダニが屋内に持ち込まれる事例が多い。
課題
- 野外活動中のマダニ接触を防ぎつつ、活動性や快適性を損なわないこと。
- ペット(犬・猫)への寄生を防ぎ、人間への二次感染も阻止すること。
- 活動後の迅速なマダニ検出と除去を可能にすること。
発明の概要
本発明は、着用型防護・ペット用対策・帰宅後の検出除去を一体化したシステムであり、以下の3つの構成を含む。
1. 人間用「防ダニウェア」
- 生地に**マダニ忌避加工(天然成分+マイクロカプセル化薬剤)**を施し、効果が長時間持続。
- 袖口・裾口・首回りに伸縮シール構造を採用し、マダニの侵入を物理的に遮断。
- 暑さ対策として通気構造を持ちつつ、マダニが好む暗所を作らないデザイン。
2. ペット用「防ダニ首輪+全身スプレー」
- 首輪内部に超音波発振機を内蔵し、特定周波数でマダニの接近を抑制。
- 外出前後に使用する低刺激性の防ダニスプレーをセットで提供。
- スプレーは被毛表面にナノレベルのバリア膜を形成し、マダニの付着を防止。
3. 「帰宅後マダニ検出・除去ステーション」
- 玄関に設置するマット型装置で、赤外線センサーとAI画像解析によりマダニを検出。
- ペットの足元や衣服に付着したマダニを自動吸引・捕獲する機能付き。
- 捕獲したマダニは内部でUV殺菌し、感染リスクを完全に除去。
実施形態の例
- 畑作業を終えたユーザーが帰宅時に玄関マット上を歩く。
- 同時に犬の足裏もマットでチェック・吸引。
- 衣服や首輪に付いたマダニは物理・化学・超音波の3段階でブロックされているため、屋内持ち込みはほぼゼロ。
- 捕獲データはスマホアプリに記録され、活動場所やマダニ発生状況のマップ化にも活用可能。
効果
- 人間・ペット・屋内環境の3方向から感染リスクを同時に低減。
- 農作業・登山・キャンプ・ペット散歩など、幅広いシーンで使用可能。
- 感染症予防だけでなく、発生地域モニタリングにも応用できる。
応用例
- 高齢者が多い農村地域での集団感染予防プロジェクト
- 自治体防災備蓄品としての配備
- ペットショップ・動物病院での予防パッケージ販売









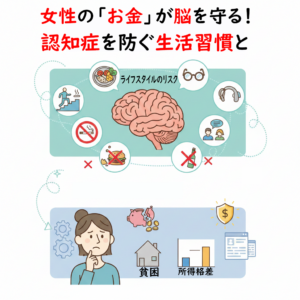

コメント