2025年9月28日、春日部交響楽団の演奏会へ行きました。プログラムはベートーヴェン交響曲第2番ニ長調作品36とブラームス交響曲第1番ハ短調作品68でした。特にブラームスの第1番、その第4楽章のある特定の瞬間に、思わず涙があふれてきました。一体、なぜこのような感情が湧き起こったのでしょうか?
脳科学的な視点からその理由を解説します(恐らくですが・・・)。
音楽による感動や情動反応は、言語や論理を司る左脳よりも、右脳や前頭前野が深く関わっています。
1. 音楽的な変化と感動の理由
例えば、ヘルベルト・フォン・カラヤンのタイムスタンプ t=1968s(約32分48秒)付近は、ブラームス交響曲第1番の第4楽章の核心部分に当たると考えられます。
https://www.youtube.com/watch?v=Lu3T0f-H3JI&t=1968s
この第4楽章は、
1.暗く劇的な序奏
2.天国的な美しさを持つホルンのコラール主題の登場
3.そして、雄大で希望に満ちた主部(コラール主題に基づく「綺麗な曲」)の提示 という、劇的な構成を持っています。
長く暗い緊張状態が続いた後、この雄大な「コラール主題」が提示される瞬間は、聴衆に解放感と強い高揚感をもたらし、しばしば涙を誘うほどの感動を引き起こすことが知られています。この劇的なコントラストとカタルシス(浄化)こそが、感情的な反応の大きな要因です。
2. 右脳と前頭前野が涙を誘う脳科学的な理由
① 右脳の役割:情動とメロディーの処理
- 感情の全体的処理: 一般的に、右脳は音楽のメロディー、ハーモニー、音色といった全体的な構造や、それらが伝える情動的な要素を処理する上で優位に機能します。
- 「感動」の直感的受容: 涙が出るほどの強い感情は、音符やリズムを論理的に分析する左脳の働き(分析的処理)よりも、音楽の全体的な響きやムードを直感的に捉える右脳の働き(全体的処理)に強く関連しています。
② 前頭前野の役割:評価と記憶の結びつき
- 高次の感情評価: 音楽を聴いて「感動した」「美しい」と感じるプロセスは、単なる反射ではなく、前頭前野(特に内側前頭前野や眼窩前頭皮質)が、その音楽を自分の価値観や過去の経験、記憶と照らし合わせて「情動的に重要である」と評価する高次な処理を含みます。
- ドーパミンの放出と報酬系: 音楽が予想外の感動的な展開(ブラームスの第4楽章のような劇的な変化)を迎えるとき、脳の報酬系が刺激され、快感物質であるドーパミンが放出されます。前頭前野はこの快感反応と連動し、感情的なピークを生み出します。
- 自律神経への指令: 最終的に、前頭前野を中心とした情動ネットワークが、涙腺を支配する自律神経系(主に副交感神経)に指令を出し、生理的な反応として涙を流させます。
結論として、ブラームスの劇的な展開を右脳が情動的に深く受け止め、それを前頭前野が「感動」として評価し、過去の記憶と結びつけた結果、情動性の涙として現れたと言えます。

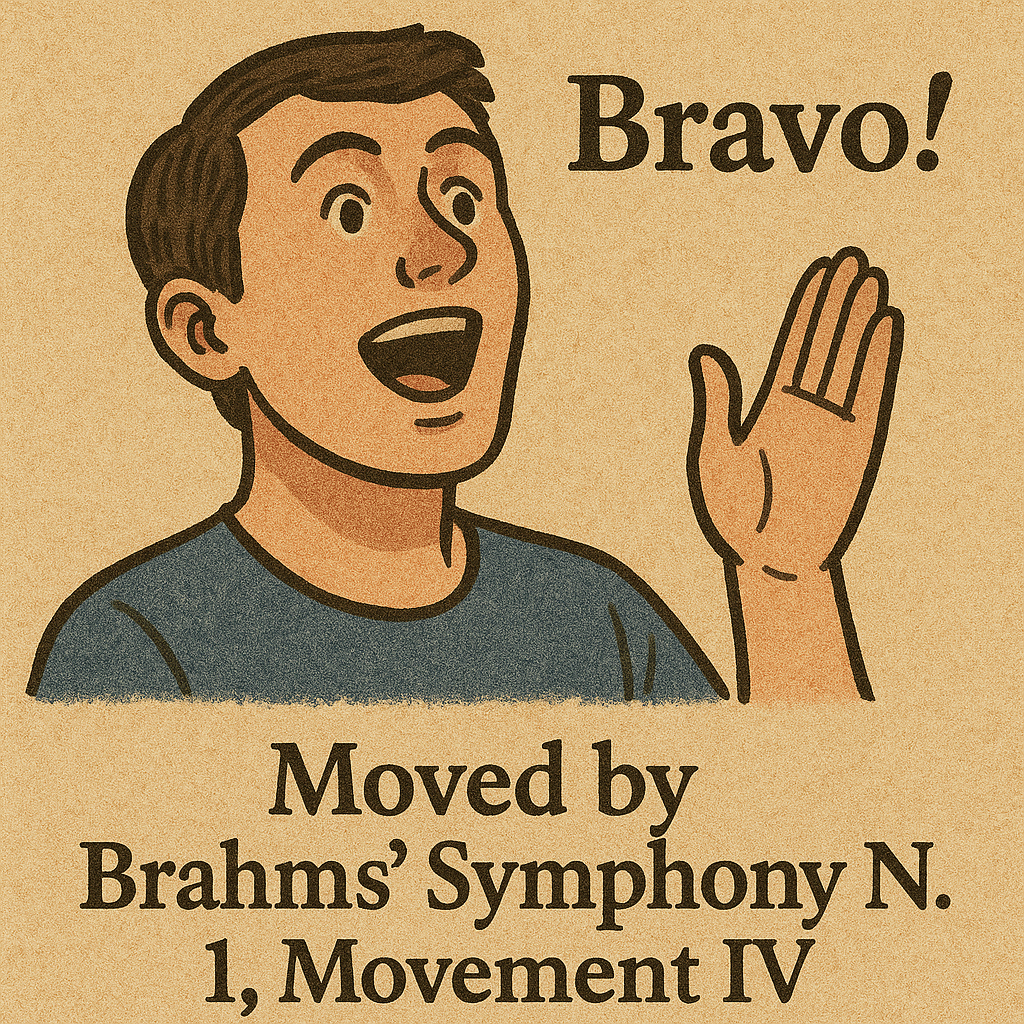
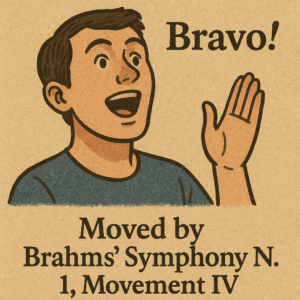


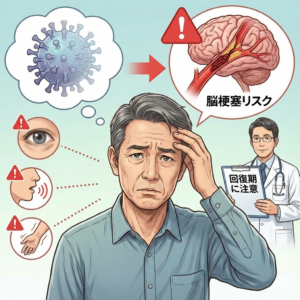
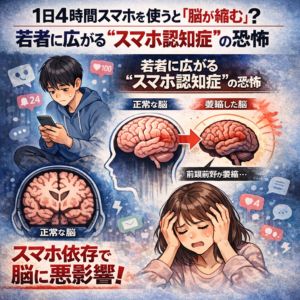




コメント