今回は、日本の未来を考える上で避けては通れない、少子高齢化という巨大な課題について、経済学者・井堀利宏名誉教授との対談をヒントに深掘りしていきたいと思います。
「このままでは日本は崩壊する」
これは決して煽っているわけではなく、現実的なリスクです。では、どうすればいいのか? 答えは 「これまでの常識を疑い、根本から視点を転換する」 ことにあると私は考えます。
1. 数字が物語る、厳しい未来予想図
政府推計では、2070年には日本の総人口が9000万人を切り、国民の約40%が65歳以上の高齢者になるとされています。これは、現役で働き、税や社会保障料を支える世代が、かつてないほど小さくなることを意味します。
年金、医療、介護。私たちが当たり前に享受してきた社会保障制度は、現役世代の支えがあってこそ成り立ちます。この支える側と受け取る側のバランスが崩れれば、制度そのものの存続が危ぶまれます。給付を減らすか、負担を増やすか——いずれにせよ、私たちの生活は確実に圧迫されます。
そして、この人口減少の最大の原因は、「出生数の減少」、つまり少子化です。
2. なぜ「少子化は止まらない」のか? ~経済的負担と見えないコスト~
井堀教授の指摘は核心を突いています。かつての日本(や現在の途上国)では、子どもは「生産財」(家業の労働力、老後の保障)でした。しかし、社会が豊かになり社会保障が整うと、子どもは「最高の贅沢品」へと変わりました。
- 経済的コストの高騰:教育費、特に大学までの費用は膨大です。IT化が進む社会では、高等教育はほぼ必須。子どもに「より良い教育を」と願えば、コストはさらに跳ね上がります。
- 機会費用の重み:これは特に女性にとって深刻です。日本では依然として、出産・育児とキャリア形成が二者択一になりがちです。仕事で活躍できる女性ほど、子どもを産むことで失うキャリアと収入(機会費用)は大きくなります。これは個人の努力の問題ではなく、社会のシステムの問題です。
- 孤独な子育ての負担:儒教的な価値観の影響も無視できません。「男は仕事、女は家庭」 といった男女の固定的役割分担意識は、相変わらず社会に根強く残っています。結果、子育ての負担は母親に偏り、「ワンオペ育児」 という言葉が生まれるほど、育児の現場は孤独とプレッシャーに晒されています。
「子どもは欲しいけど、経済的に厳しい」
「仕事も続けたいけど、育休後の職場復帰やキャリアアップが不安」
——こうした声の背景には、単なるお金の問題だけではなく、社会の構造や古い価値観が深く関わっているのです。
3. 東アジアという共通課題~儒教文化圏が抱えるジレンマ~
日本の少子化は特別ではありません。隣国の韓国は出生率0.72(2023年)と世界最低水準です。中国、台湾も同様に深刻な少子化に悩まされています。
これら東アジア諸国に共通するのは、儒教文化の影響を受けた社会規範です。学歴競争の激しさ、家族への過度な期待、そして男尊女卑的な価値観。これらが相まって、子育てのコストとプレッシャーを異常に押し上げている側面は否めません。
4. では、何を「視点転換」すればいいのか? ~崩壊への道を変えるための提案
ここからが本題です。この現状を打破するには、小手先の政策ではなく、社会の根幹にある「ものの見方」そのものを変える必要があります。
① 「男尊女卑」から「真の男女共同参画」へ
これは最も重要な視点転換です。「育休を取る男性はカッコ悪い」「家事・育児は女の仕事」といった古い価値観を捨て去らなければなりません。育児は「母親の責任」ではなく「社会全体で支える共同作業」 であるという認識に立つ。企業は、男性の育休取得を当然の権利として推進し、女性がキャリアを中断せずに働き続けられる環境を整備する。政治は、それを後押しする法整備とインセンティブを設ける。この変革なくして、機会費用の問題は解決できません。
② 「子どもは私費」から「子どもは社会の共通財」へ
子育てのコストを「個人の負担」と捉えるのをやめ、社会全体で分かち合う投資であると考える視点転換です。幼児教育・保育の無償化をさらに推進し、高等教育の負担軽減(給付型奨学金の拡充など)を大胆に行う。子どもを産み、育てることが、経済的に「割に合わない」選択ではなくなる土壌を作る必要があります。
③ 「均一な働き方」から「多様な働き方」へ
終身雇用・年功序列を前提とした画一的な働き方は、子育て世代の柔軟な働き方の足かせになっています。テレワーク、時短勤務、副業など、多様な働き方を評価し、活躍できる機会を提供する企業文化への転換が不可欠です。これは、働く親だけでなく、高齢者や障害者など、あらゆる人々が活躍できる社会への第一歩です。
④ 「閉鎖性」から「開放性」へ
人口減少が確実である以上、国外からも人材を受け入れ、活力を注入することは必須の選択肢です。「移民」という言葉に過度に拒否反応を示すのではなく、多文化共生社会をどうデザインするかという建設的な議論に視点を移す時期に来ています。
おわりに:未来は諦めない選択から
少子高齢化は、私たち一人ひとりの生活に直結する、待ったなしの課題です。
「自分には関係ない」「どうせ変わらない」と諦めるのは簡単です。
しかし、この国の未来は、私たちの「選択」と「視点の転換」にかかっています。これまでの常識や価値観に縛られず、より多様で、柔軟で、誰もが生きやすい社会を構想する。子育てを「個人の責任」から「社会の喜び」に変えていく。
その第一歩は、この問題を他人事ではなく「自分事」として捉え、議論し、行動を始めることから始まるのではないでしょうか。
読者への問いかけ:
あなたは日本の未来についてどう考えますか?
どんな「視点の転換」が必要だと思いますか?
ご意見、コメントをお待ちしています。








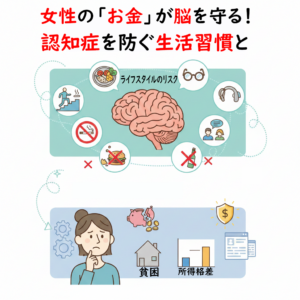

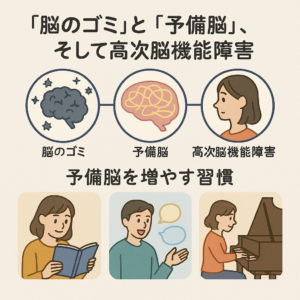
コメント