2025年、アメリカでは再び政治の嵐が吹き荒れています。全米50州で約60万人が参加した大規模な抗議デモ。「トランプは退陣を」と叫ぶ人々の声は、政権の強権的な政策と、公共サービスの削減に対する深い怒りを反映しています。
ワシントン記念塔の周辺には数万人が集まり、「独裁者にノー」「プーチンの操り人形」といったプラカードを掲げました。その中でも注目を集めたのが、イーロン・マスク氏の「政府効率化省(DOGE)」による教育、医療、社会保障の大幅削減に反対する声です。
ここで注目したいのは、こうした政治の動きが、特許や技術開発、そして障がい者の暮らしにどんな影響を与えるのかという視点です。
テクノロジーと障がい者をつなぐ「特許」
特許制度は、革新的な技術を社会に届けるための仕組みです。しかしこの制度は、大企業や研究者だけのものではありません。実は、障がい者自身が日常生活の中で得た「気づき」や「工夫」こそが、社会を変える力を秘めています。
たとえば、車椅子ユーザーが考案した自動スロープ、自閉症の子どもと接する親が開発した支援アプリ、失語症の方が使いやすいコミュニケーションツールなど──。**障がい者の経験は、生活に密着した「本当に必要な発明」**を生み出しているのです。
ところが、今回のような公共支援の削減は、そうした発明を形にする機会を奪ってしまいます。研究費、補助金、アクセシブルな特許支援制度などがなければ、障がい者のアイデアは「埋もれた可能性」のままで終わってしまうのです。
民主主義とアクセシビリティ
特許制度そのものは、平等な仕組みに見えます。しかし、障がい者にとっては「アクセスのしやすさ」が非常に重要な課題です。
たとえば、手の自由が利かない人にとっては、電子出願の操作が難しいことがあります。失語症の方にとっては、書類作成や技術的説明文の表現が大きな壁になることもあります。こうした「見えないバリア」を取り除く支援こそが、社会的包摂に向けた本質的な取り組みです。
特許庁や自治体が提供するサポートがなければ、障がい者の創造的な知見は発明として形になりません。その意味でも、公共支援の削減は、単なる予算の問題ではなく、技術の多様性を損なうリスクを伴っています。
技術は誰のものか?
私たちは今、問い直す時期に来ています。
「技術は誰のためにあるのか?」
トランプ政権が進める効率化と自己責任の論理の中で、障がい者や弱者が置き去りにされている現実があります。しかし、技術の本来の目的は、人々の生活を少しでも豊かに、便利に、安全にすることにあるはずです。
障がい者が自分の言葉で話せるようになる技術、聴覚や視覚の代わりになるデバイス、移動の自由を実現する発明──こうした技術を特許として守り、広げることが、これからの社会に必要不可欠です。
まとめ:障がい者による「社会を変える発明」を支える仕組みを
抗議デモは声を上げる手段ですが、特許もまた、静かに社会を動かす「もう一つの表現方法」です。障がい者が発明者として活躍できる社会は、多様な視点を受け入れる社会です。そしてそのためには、政治・経済・技術・知的財産のすべてが、有機的に連携する必要があります。
誰もが発明できる。
誰もが社会を変えられる。
そのための環境を守ることが、今まさに問われています。


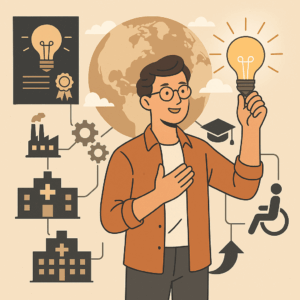

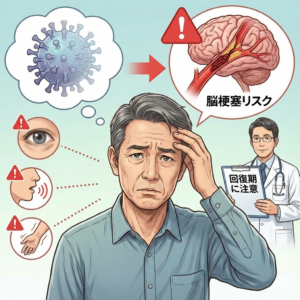
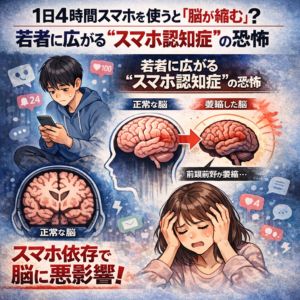
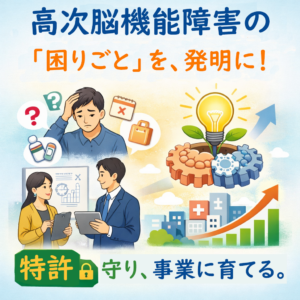


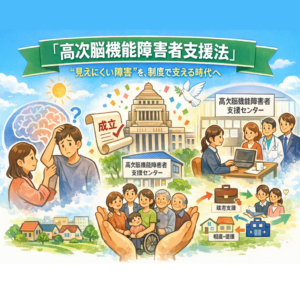

コメント