今日は「失語症の日」です。失語症とは、脳の障害によって「言葉をうまく話す・聞く・読む・書く」が難しくなる状態を指します。日本では、年間5万人以上の人が脳卒中などで失語症を発症していると言われています。しかし、多くの人にとって、失語症はまだまだ知られていない障害のひとつです。
失語症は「言葉の交通事故」
失語症は、よく「言葉の交通事故」とたとえられます。
たとえば、脳の中にある「言葉を出す工場」と「言葉を理解する工場」を結ぶ道路が事故で寸断されたようなイメージです。考えはちゃんとあっても、うまく言葉にできない。逆に、話しかけられても意味がつかめないこともあります。
ここで大事なのは、「本人の知能が低下しているわけではない」ということです。あくまで、「言葉を使う機能」が壊れているだけなのです。
「わかっているのに言えない」苦しさ
失語症の人は、**「言いたいことがあるのに言えない」**という悔しさを常に感じています。たとえば、
- お店で「水」と言いたいのに、「お茶」と言ってしまう
- 名前を知っているのに、口から出てこない
- 質問されても、何を聞かれているかわからない
周囲から見ると「なんだか変なことを言っているな」と思われるかもしれません。でも、本人にとっては必死に伝えようとしているのです。
新しい視点――失語症は「コミュニケーションの多様性」
ここで、少し新しい考え方を紹介します。
これまで、失語症は「できないこと」「不自由なこと」と捉えられてきました。でも最近では、**「コミュニケーションの多様性」**と考える動きもあります。
たとえば、
- ジェスチャーや絵カードを使って伝える
- 表情や気配で想いを届ける
- 短い単語だけで会話を成立させる
こうした方法も、立派な「人と人とのつながり」です。
失語症だからこそ生まれる、あたたかいコミュニケーションがあるのです。
支えるためにできること
私たちにできるサポートは、難しいことではありません。
- ゆっくり話す
- 簡単な言葉を使う
- 待つ(焦らせない)
- 伝え方を工夫する(ジェスチャーやメモを使う)
何よりも大切なのは、「急がない」「見守る」という姿勢です。
失語症支援に役立つ「特許アイデア」
ここで、失語症の方を支えるための新しい特許アイデアも紹介します。
【特許&アイデア】
私は、5件の特許を作成し、特許庁へ提出しました。
「失語症者向け意思表示支援メガネ」
- 音声認識ではなく、目線の動きで意思を伝える
- たとえば、
- 「水」や「トイレ」などの基本ニーズがメガネ内に表示
- 見つめた文字や絵を、周囲にスマホ経由で音声出力
- 手が動かなくても、声が出なくても、**「目で伝える」**ことができる
これにより、失語症の方ももっと自由に、確実に意思表示ができる社会を目指せます。
まとめ
4月25日、失語症の日。
この日は、単なる「啓発」だけではなく、
**「ことばを交わす喜び」**を改めて感じる日でもあります。
失語症は、単に「不自由」なのではなく、新しいコミュニケーションの形を教えてくれるもの。
みなさんも今日、この機会に、「言葉」のありがたさを、そして「伝える力」の大切さを、少しだけ見つめ直してみませんか?

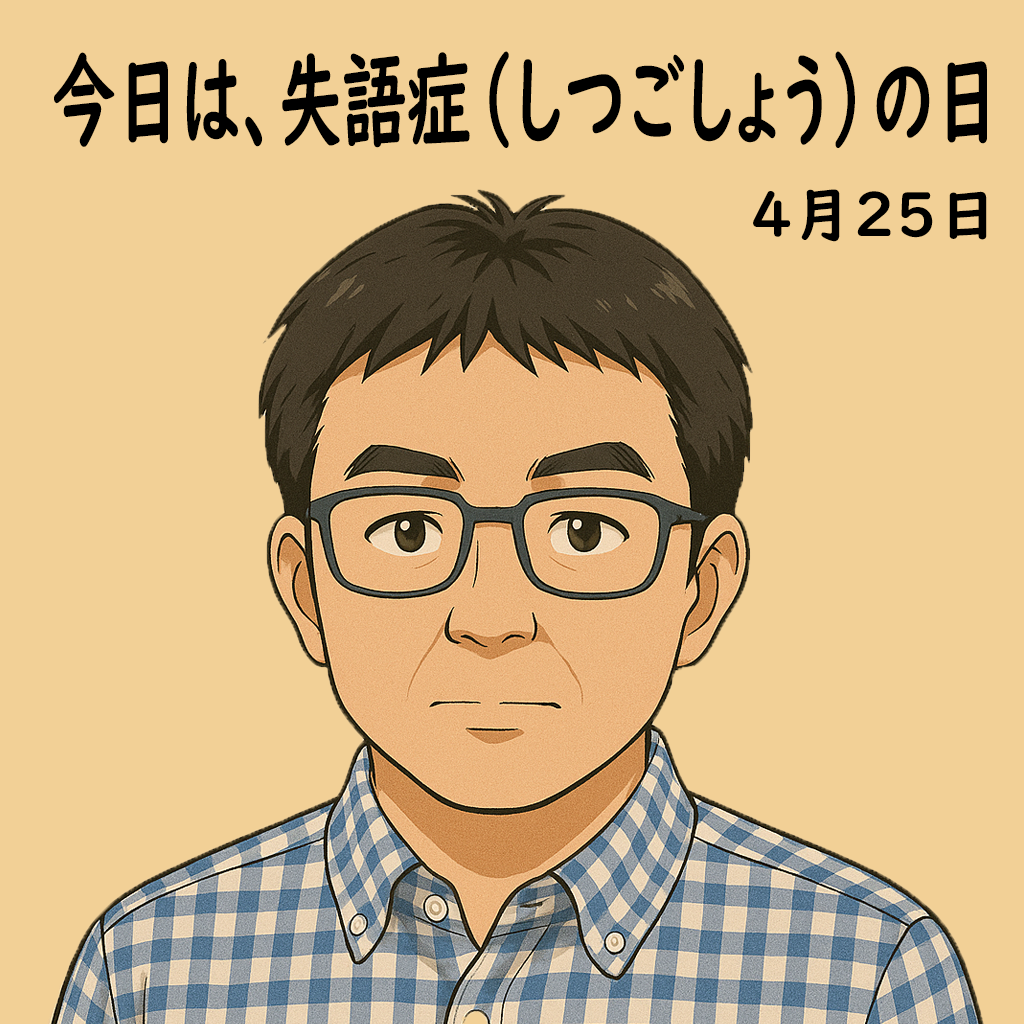

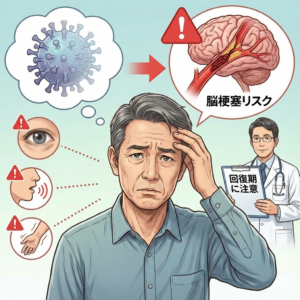
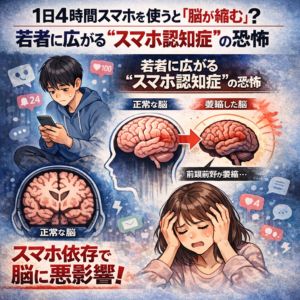

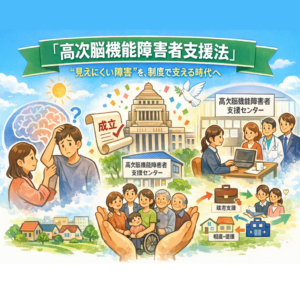
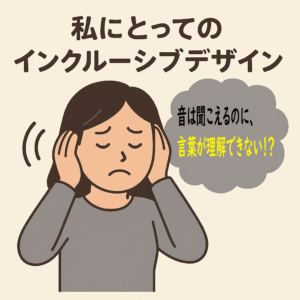

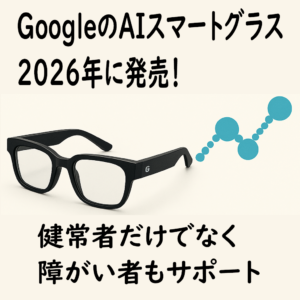
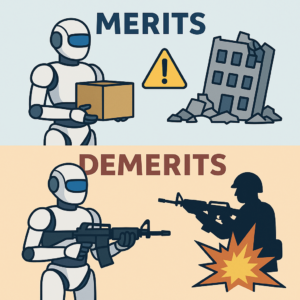
コメント