要約(Summary)
失語症者の経験から、英語のほうが日本語よりも理解しやすく感じる事例を紹介。東京大学の「授業英語化」の議論を背景に、言語と思考の関係、多言語の可能性について考察。母語以外でも深い思考は可能であり、教育や社会構造は多言語化への対応が求められる。あわせて、失語症者や外国人向けの「マルチリンガルAIノート」特許を提案。
はじめに
私は、失語症になりました。脳梗塞を発症したのは55歳のとき。それまで当たり前に使っていた言葉が、ある日突然出てこなくなったのです。特に日本語の「漢字」は難しく、平仮名・片仮名(五十音)でさえ時間がかかることがあります。
けれど不思議なことに、英語はあまり苦になりません。脳梗塞前にTOEICスコアは940あり、今でも比較的スムーズに読んだり書いたりできます。日本語が母語の私にとって、この現象はとても興味深いものでした。
ちょうどそんな折、東京大学大学院が「授業の英語化」を発表したことが話題になりました。この記事では、私の失語症の経験と、東大の英語化方針、そして多言語話者の意見を通じて、「言語」「思考」「学び」の未来について考察してみます。
英語のほうが「やさしい」と感じるのはなぜか?
私の失語症では、「文字の認知」に大きな障害が生じました。特に漢字は複雑で、構造を認識して意味を思い出すのに時間がかかります。一方で、英語はアルファベットという記号の組み合わせであり、文字数も少なく構成も直線的なため、視覚的にも認知的にも処理が軽いと感じます。
さらに、英語は文法構造が明快です。語順が固定されており、「主語 + 動詞 + 目的語」という形が一貫しているため、文の全体構造を捉えやすいのです。
日本語では、「てにをは」や敬語、文脈依存性など、暗黙のルールが多く、文法や意味の解釈に高い認知力が必要です。失語症者にとっては、この「曖昧さ」こそが最大の壁です。
東大の「授業英語化」は誰のためか?
東京大学大学院工学系研究科は、2025年度から一部授業を英語で行い、翌年からは原則英語で実施する方針を打ち出しました。背景には、国際競争力の強化や、多様な学生の受け入れ、リーダー育成などの目的があります。
東大生の意見は二分されました。
- 「日本語の方が理解できるし、学問の伝統を大事にしたい」
- 「英語で最先端研究にアクセスできるのは必要」
- 「日本語が得意でない留学生には助かる」
- 「でも、深く思考するには母語でないと難しいのでは?」
このように、**言語の選択が「理解力」「思考の深さ」に影響を及ぼすのか?**という問いは、私の失語症経験とも重なります。
7カ国語話者・ファリザ氏の視点:言語は人格を変える
タジク語を母語とし、ウズベク語・ロシア語・英語・日本語・ペルシャ語・トルコ語の7カ国語を話すファリザ・アビドヴァ氏は、「母語以外でも深い思考はできる」と語っています。
彼女にとって、英語や日本語のほうが、むしろクリエイティブで深い思考ができるとのこと。これは言語が単なる「道具」ではなく、「思考の型」や「人格の一部」になっていることを示唆しています。
私自身、英語を使っているときのほうが論理的に考えられ、文章も構造的に整理しやすいと感じることがあります。これは決して偶然ではなく、言語が思考を形づくるという証明ではないでしょうか。
言語の「障害」から見える、教育の未来
失語症の私にとって、「言語とは何か?」という問いは切実です。
「英語ができるかどうか」ではなく、「どの言語で自分の思考をうまく表現できるか」という視点で、言語教育や研究環境を考え直す必要があると思います。
また、日本語に偏った教育や社会構造が、実は“見えない障害”を作っている可能性もあります。外国人労働者や留学生、高齢者、発達障害者など、日本語にハンディのある人に対して、英語や他言語での支援を前提とする社会が、よりフェアで開かれたものになるのではないでしょうか。
提案:特許アイデア「マルチリンガルAIノート」
このような背景を踏まえ、以下のような特許技術を提案します。
【発明の名称】
失語症者・外国人・高齢者向け 多言語対応AIノートシステム
【概要】
- 日本語/英語/他言語の自動翻訳と並列表示機能
- 難読文字にはふりがな/意味画像/音声読み上げ
- ユーザーの習得状況に応じた忘却曲線ベースの復習提案
- 発話・会話履歴から学習状況を自動解析
- タブレット・スマホ対応で家庭でも使用可能
【応用例】
- 東大などの大学のバイリンガル講義補助ツール
- 失語症者の言語リハビリ支援
- 外国人労働者向けの業務教育支援
- 高齢者の認知リハビリ支援
おわりに:言語とは「思考とつながる橋」
「日本語は母語だから得意」
「英語は外国語だから苦手」
そう信じてきた固定観念を、私は失語症を通じて大きく疑うことになりました。
英語の方が「わかりやすい」こともある。日本語が「重すぎる」こともある。
そして何より、「母語」よりも「使いやすい言語」が人それぞれにあるという事実です。
言語とは、知識を得るための道具ではなく、**自分の思考を育てる“脳の外側”**です。
その「外側」が使いやすい形になっていれば、人はもっと自由に、深く、学べるはずです。
学び(Learning)
- 言語は単なる知識の道具ではなく、思考の型を左右する。
- 失語症者のように「母語に困難を感じる人」が見えると、言語教育の在り方も変わる。
- 多言語を使うことで、コミュニケーション力だけでなく、発想や人格までも広がる可能性がある。
新しい視点(New Perspective)
- 「母語=最も深く考えられる言語」という前提を問い直す。
- 教育や社会システムは、日本語が苦手な人にも開かれるべきである。
- 言語の選択は、障害支援・多文化共生・高齢社会への対応にも直結する。

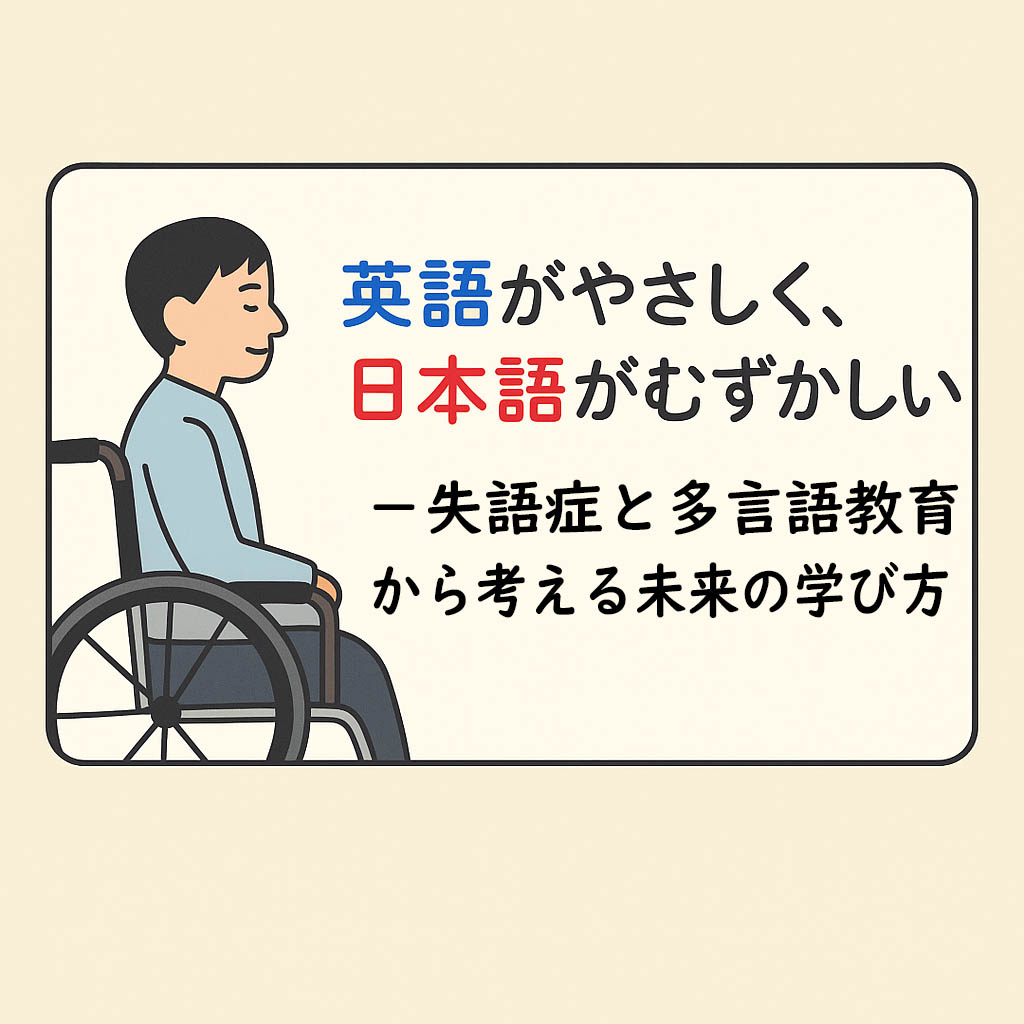


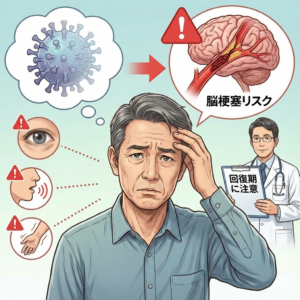




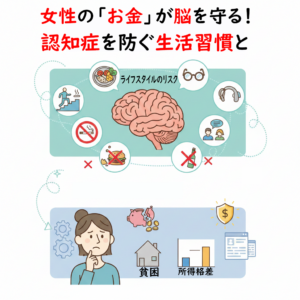

コメント