- 史料(侍医の拝診書・御容態書、日記、『大正天皇実録』など)を読み直すと、言語障害が最初に目立ち、その後に認知・運動障害が広がった経過が確認できる。J-STAGE
- このパターンは原発性進行性失語症(PPA)、とくに非流暢/失文法型で説明できる可能性が高い。一方、初期の障害が「失語」ではなく構音(発音運動)障害と解釈されるなら**大脳皮質基底核症候群(CBS)**という仮説も成り立つ。J-STAGE
- いずれも確定診断は不可能だが、学術的には**「失語を主とする高次脳機能障害」**として位置づけるのが妥当、というのが近年の見解である。J-STAGE
目次
何が起きたのか(史料にもとづく経過)
- 1914年(大正3):発話障害で発症(失語の可能性。ただし構音障害の可能性も記載)。
- 1915年:前屈姿勢が出現、階段昇降に介助が必要。
- 1918年:発語障害が増悪、軽度の記憶障害。
- 1919年:歩行障害。
- 1921年末:判断・思考の障害が進み、認知症へ。
この**「言語→(徐々に)認知・運動へ」**の広がりは、変性疾患としての失語(PPA)の典型的な時間軸と合致する。J-STAGE
医学的にどう見えるか
1) 原発性進行性失語症(PPA)仮説
- PPAは、前頭葉・側頭葉・頭頂葉の一部に生じる変性(萎縮)により、言語障害が最初に顕著に現れる病型。のちに障害が他領域へ広がることがある。日本神経学会
- 大正天皇の経過は**非流暢/失文法型(nfvPPA)**の特徴(話しにくさ、発話の非流暢、文法障害)と矛盾しない。近年のnfvPPA症例報告でも、発語運動障害と文法障害が併発しうることが示されている。J-STAGE+1
2) 大脳皮質基底核症候群(CBS)仮説
- 初期の「発語障害」を失語ではなく構音障害/発語失行とみなし、かつ姿勢の前屈・歩行障害など運動症状の進行を重視すると、CBS(前頭側頭葉変性症の一亜型)として説明できる余地がある。J-STAGE
簡単に言うと:
先に「ことば」が崩れて、その後「考える・歩く」に広がったならPPAっぽい。
先に「発音運動の不具合+姿勢・歩行の問題」ならCBSも考えられる。
「高次脳機能障害」と「失語症」の関係(超要点)
- 高次脳機能障害:記憶・注意・遂行・言語など、脳の“高度なはたらき”の障害の総称。
- 失語症:ことばの理解・表出の障害で、高次脳機能障害の一種。
- PPAは変性疾患としての失語症で、言語障害が最初に前景化するタイプ。日本神経学会
なぜ断定できないのか(歴史の診断の限界)
- 当時はMRI/CTや病理確認がない。
- 史料は症状描写が中心で、言語検査の標準化データがない。
- PPAもCBSも症状が重なりうるスペクトラムで、現代でも鑑別が難しい。日本神経学会
よくある誤解と事実
- 「精神疾患だった?」→ 否定できないが、一次史料に基づく現代の再解釈は、まず**神経変性疾患(PPA/CBS)**を第一に考える立場。J-STAGE
- 「幼少期の“髄膜炎様”の病歴=直接原因?」→ 直接因果は不明。ただし鉛中毒が疑われる幼少期の脳疾患歴はリスク要因の仮説として論じられている。CiNii Research
私たちが学べること(臨床・支援の視点)
- 最初の症状が何か(言語か、発音運動か、運動・姿勢か)で、その後の見立てや支援計画は変わる。
- 時間とともに領域が広がるのが変性疾患の特徴。環境調整とコミュニケーション支援(文字支援、要約筆記、キーワード提示、ゆっくり・短文で話す等)が重要。
- 歴史症例の検討は、**失語症=単一の病名ではなく「症候」**であること、背景病態(脳梗塞・変性・炎症など)を分けて考える重要性を教えてくれる。
まとめ
- 記録に照らせば、**「失語を主とする高次脳機能障害」**としての発症像がもっとも自然に説明でき、第一候補はPPA(非流暢/失文法型)。
- ただし、構音障害優位の読みを採ればCBS仮説も成立しうる。
- 確定診断は不可能だが、歴史資料×現代神経心理学の観点からは、この二仮説の枠組みで理解するのが妥当である。J-STAGE



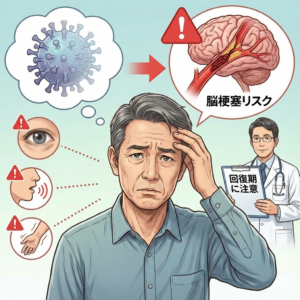


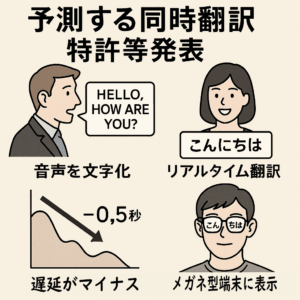


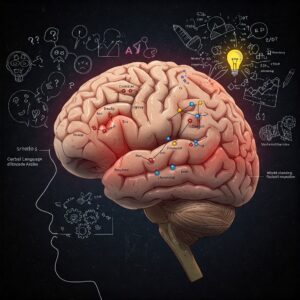

コメント