「クマを駆除すべきか、否か?」
この問いは単なる動物管理や安全対策にとどまらず、私たちの中にある「論理」と「感情」のせめぎ合いを浮き彫りにします。近年、日本各地でクマによる人身被害が増加し、自治体や住民は「駆除」という判断を迫られる場面が増えています。
一方、SNSやメディアでは「かわいそう」「クマは悪くない」といった感情的な声も多く見られます。こうした対立の背景には、人間の脳の仕組みと社会制度の関わりが深く横たわっているのです。
1. 「左脳 vs 右脳」――伝統的な簡易モデル
かつては、「論理は左脳、感情は右脳」とするシンプルな分類がよく語られてきました。
- 左脳:言語、分析、計算に優れ、論理的思考の中枢
- 右脳:直感やイメージ、感情を司る「感性の脳」
このモデルに照らせば、「駆除すべきか」と理詰めで考えるのは左脳的、「クマが可愛いから殺したくない」と感じるのは右脳的といえるでしょう。
左脳的判断の例:
- クマによる人身被害の統計
- 地域社会や農業への経済的影響
- 生態系バランスの管理や対策コスト
右脳的反応の例:
- ふわふわした毛並み
- つぶらな瞳と丸いフォルム
- 「くまのプーさん」や「リラックマ」などへの親近感
こうした感情が強くなるほど、駆除への反発も大きくなります。
2. 現代神経科学――脳はもっと複雑
現在の神経科学の研究では、「左脳 vs 右脳」という単純な二分法は否定されています。感情も論理も、脳全体のネットワークによって複雑に処理されていることが明らかになっています。
「可愛い」と感じるとき:
- 扁桃体:恐怖や愛着などの感情を処理
- 側坐核:報酬系に関わり、「心地よさ」を感じる
- 前頭前皮質:共感や判断の調整に関与
- 言語中枢(左脳):「かわいい!」と表現する際に活性化
「駆除すべきか」と考えるとき:
- 前頭前皮質が中心となって論理的に判断
- しかし、「殺すのは可哀そう」という感情中枢の働きも強く影響
つまり、私たちの判断は単独の脳領域で行われるのではなく、感情と理性が並行して働くネットワーク構造で決まっているのです。
3. クマ駆除をめぐる社会的対立
SNSや地域での議論を見てみると、脳の働きの違いがそのまま反映されていることに気づきます。
感情的な反対意見(右脳優勢):
- 「自然の中で生きているだけで、人間が悪いのでは?」
- 「無辜(むこ)の命を奪うのは残酷」
- 「母グマを失った子グマが可哀そう」
これらは、感情・共感・倫理観に基づいており、映像や写真によって一層強化されます。
論理的な賛成意見(左脳優勢):
- 「過去に人が襲われた事例が多い」
- 「地域の安全確保には駆除が必要」
- 「対策コストを考慮すると現実的」
ただし、感情の強さがデータの受け入れを妨げる場合もあります。
4. 判断は「感情 × 論理 × 環境要因」の掛け算
人間の判断は、論理と感情のどちらか一方で決まるのではありません。両者がせめぎ合い、状況や個人の価値観によってバランスが変化します。
たとえば、
- データでは「駆除が妥当」と分かっていても、感情が強く反対すれば、行動にブレーキがかかる。
- 感情的には「殺したくない」と思っても、「家族や地域の安全」を考えれば、駆除に賛成する人もいる。
こうした多様な視点が存在するからこそ、社会的な合意形成が難しいのです。
5. 「可愛い」と感じるのは本能的な反応
心理学者コンラート・ローレンツは、「ベビースキーマ」という概念を提唱しました。丸い顔、大きな目、短い手足などの特徴を持つ存在に対して、人間は本能的に「守りたい」と感じるのです。
これは赤ちゃんに限らず、子犬、パンダ、そして子グマにも当てはまります。だからこそ、「クマが可愛い」と感じる感情は自然であり、同時に判断を曇らせる要因にもなるのです。
6. 法律的観点――ルールに基づく判断の必要性
感情や倫理観も大切ですが、社会として一貫性のある判断を行うためには、法律という共通のルールに基づいた対応が不可欠です。
1. 鳥獣保護管理法の存在
日本では「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、熊の捕獲・駆除は原則として許可制です。無許可の駆除は違法行為であり、罰則も定められています。
2. 正当な理由と手続き
人命への危険や農業被害など、明確な理由がある場合のみ、都道府県知事などの許可を得て駆除が行われます。市街地に現れた場合など、緊急対応も別途規定されています。
3. 動物愛護とのバランス
熊も命ある存在であり、安易な駆除ではなく「追い払い」「捕獲・移送」などの代替手段の検討も、法律の中で重要視されています。
4. 自治体の対応マニュアル
多くの自治体は、「熊出没対応マニュアル」や「有害鳥獣駆除マニュアル」を整備しており、住民・行政・猟友会の連携や、駆除のルールと責任の明確化が求められています。
結論:クマを駆除すべきか――脳と法で向き合うべき問い
「クマを駆除すべきか?」という問いには、人間の本質が表れています。
私たちの脳は、「可愛いから守りたい」「でも危険だから排除すべきだ」という感情と論理の葛藤を抱えながら判断を下します。そしてその判断を社会全体で共有し、実行するには、法律という共通ルールの存在が不可欠です。
つまり、クマの駆除をめぐる判断には、
- 感情(右脳)
- 論理(左脳)
- 法律という社会的枠組み
- 科学的データという客観性
このすべてが複雑に関与しています。
人間の脳の仕組みと、法による社会的合意の重要性を理解すること。
その両立こそが、クマと人間の共生、あるいは安全な共存に向けた冷静で建設的な議論の出発点となるのではないでしょうか。


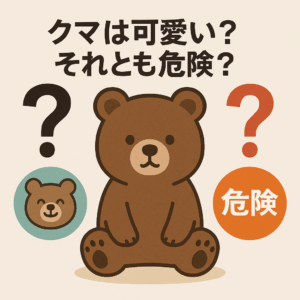






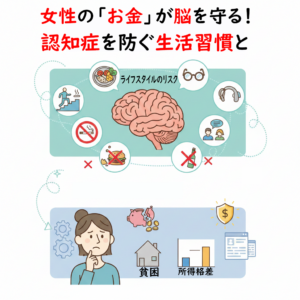

コメント