スマホ認知症と高次脳機能障害とは?
私たちは日々、物忘れに直面します。「あれ、あの人の名前なんだっけ?」「最近、漢字が思い出せない」「なんでここに来たんだっけ?」──そんな経験、誰にでもあるはずです。しかし、その“忘れ方”には大きな違いがあるのです。
最近話題となっている「スマホ認知症」という言葉をご存知でしょうか?スマートフォンの使いすぎにより、記憶力や集中力が低下し、一時的に認知症に似た症状が現れる現象です。一方で、「高次脳機能障害」と呼ばれる状態は、脳卒中や事故などにより脳の一部が損傷し、言語や記憶、注意、実行機能などに長期的な障害が生じるものです。
この記事では、筆者自身の体験をもとに、「スマホ認知症」と「高次脳機能障害」の違いを明らかにしながら、「忘れること」の本質について考えてみたいと思います。
私はスマホではなく、パソコンを毎日使っている
筆者は60歳で、2019年に脳卒中を経験し、現在は高次脳機能障害の一つである「失語症(ウェルニッケ型)」を抱えています。言葉を理解する力や、自分の考えを言葉にする力が弱くなり、特に口頭でのコミュニケーションが困難です。
しかし、文字での表現は今でも可能です。ブログ、SNS、メール、動画制作などを通して、毎日発信を続けています。スマートフォンも使いますが、主に使っているのはパソコンです。ニュースを読むのも、調べ物をするのも、メモを取るのもすべてPCです。
ところが、以下のような症状が続いています:
- 知っている人の名前がすぐに出てこない
- 最近、漢字が書けなくなった
- 忘れないようにすぐ写真を撮る
- 紙の本や辞書を使わない
- 仕事や家事の段取りがうまくいかない
このような状態を見たとき、「もしかして自分もスマホ認知症?」と心配になる方も多いかもしれません。でも、実際はそうではありません。これは高次脳機能障害の典型的な症状なのです。
「スマホ認知症」と「高次脳機能障害」の違いとは?
スマホ認知症
「スマホ認知症」とは医学用語ではなく、現代のデジタル生活による脳の疲労や情報過多に伴って生じる一時的な記憶障害や注意力低下を指す俗称です。以下のような特徴があります:
- 原因:スマホの使いすぎ、情報過多、睡眠不足
- 症状:名前が出ない、段取りが悪くなる、集中できない
- 対策:デジタルデトックス、生活習慣の改善、運動や自然体験
- 改善:休めば回復することが多い
高次脳機能障害
一方、「高次脳機能障害」は脳の損傷によって生じるもので、次のような特徴があります:
- 原因:脳卒中、外傷、脳炎、脳腫瘍など
- 症状:記憶障害、注意障害、言語障害、遂行機能障害など
- 対策:専門的なリハビリ、支援機器、生活の工夫
- 改善:回復には長い時間と支援が必要
見た目では区別できない──だからこそ誤解される
スマホ認知症も高次脳機能障害も、「物忘れ」「集中できない」「段取りが悪い」など、表面上の症状は似ています。だからこそ、周囲からは「年のせいじゃない?」「スマホのせいだよ」と言われがちです。
しかし、原因と回復の道筋がまったく異なるため、本人にとっては非常に苦しい誤解となります。
筆者も、話すことが難しいために「ボーッとしてる」と思われたり、「スマホの見すぎ」と誤解されたことがあります。本当は、脳の損傷によってうまく言葉が出てこないだけなのです。
「忘れる」ことの本質とは?
人間の脳は「覚える」ことと同じくらい、「忘れる」ことも大切な機能です。問題は、それが「必要なときに思い出せない」状態が日常生活に支障をきたすレベルかどうかです。
- 一時的な情報過多によるもの → スマホ認知症のような状態
- 脳の神経ネットワークの損傷 → 高次脳機能障害
それぞれの状態に応じた対応と理解が必要です。
脳を守るには?──共通する対策もある
スマホ認知症と高次脳機能障害は異なるものですが、脳の健康を守るために共通して有効な方法もあります:
- 睡眠をしっかりとる
- 脳に優しい食生活(地中海食など)
- 軽い運動や散歩
- 自然とのふれあい(森林浴など)
- 人との交流、会話(失語症の場合はテキストも可)
- 紙に書く、手を使う習慣(メモ、家事など)
おわりに──理解と共生の社会へ
筆者のように高次脳機能障害を抱えながらも、パソコンやSNSを通じて発信を続けている人間もいます。スマホ認知症と誤解されることもありますが、それぞれの「見えにくい困難」には、異なる背景と支援が必要です。
これからの社会は、表面的な判断ではなく、「なぜそうなっているのか?」を丁寧に理解し、共に生きる工夫が求められています。
「忘れる」ことを恐れすぎず、「どうすれば思い出せるか」「どう支え合えるか」を考える。それが、私たちの未来を少しずつ明るくしていくと信じています。

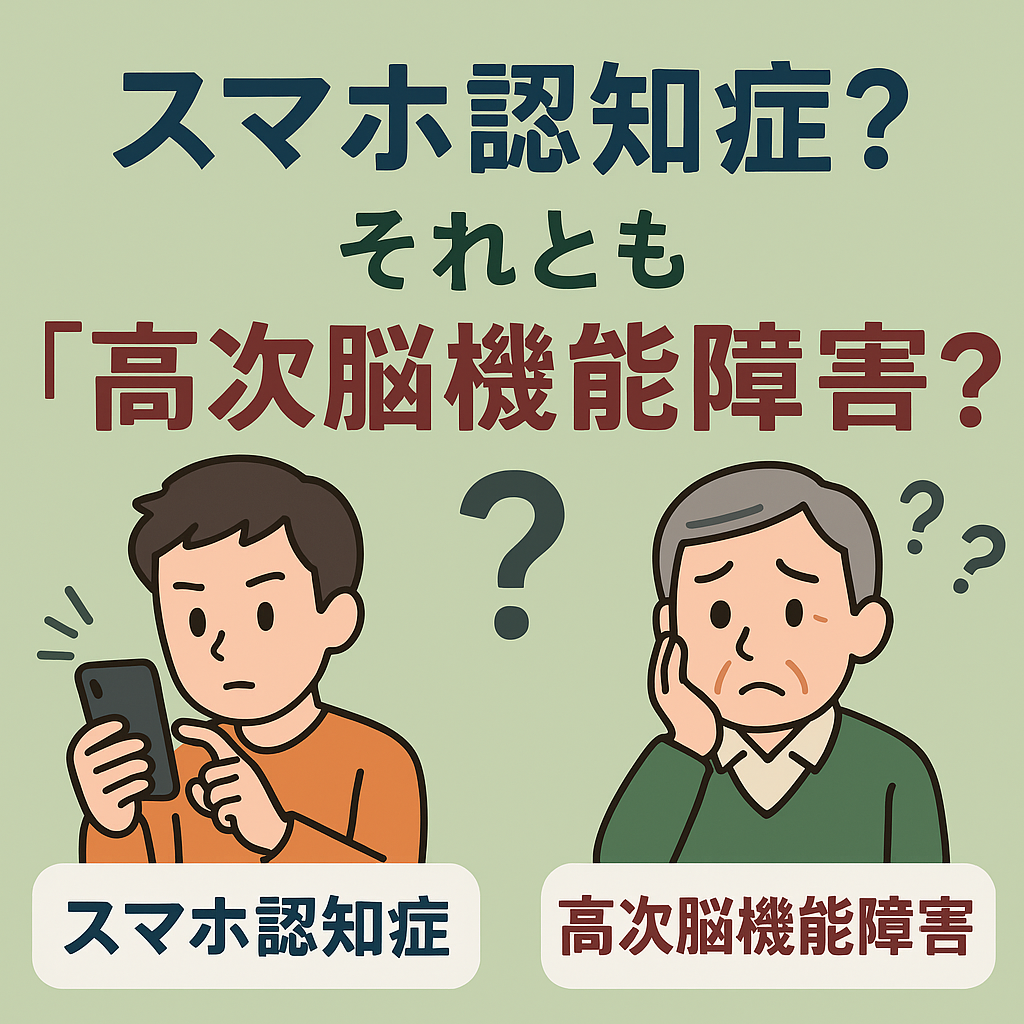
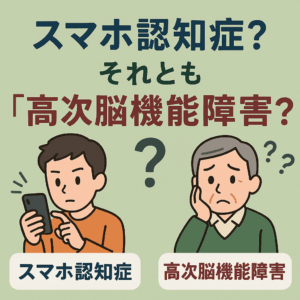


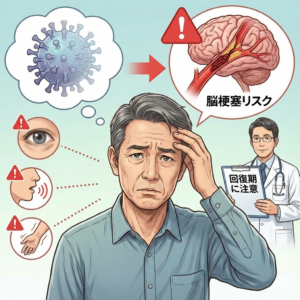
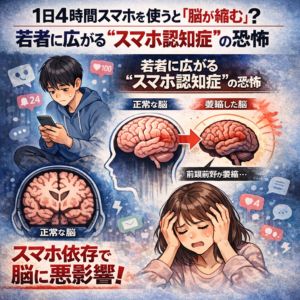
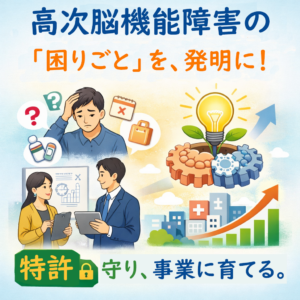

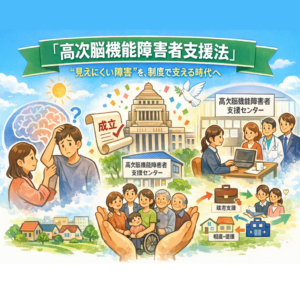

コメント